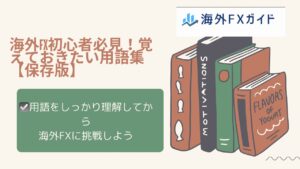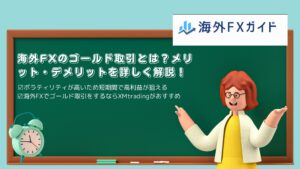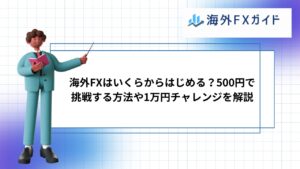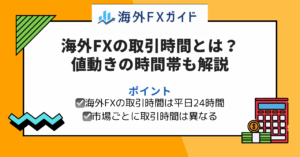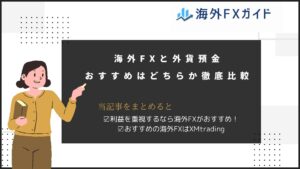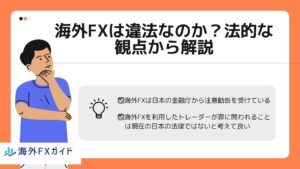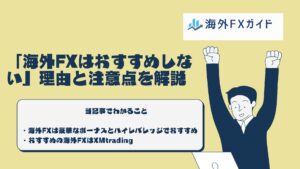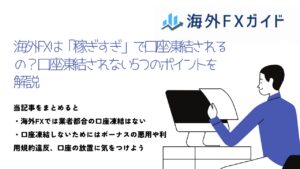少ない資金で取引を行い、誰でも手軽に利用が開始できるのはFXの魅力です。このFXで取引を行い利益が出ている方々も多いはずです。
 モルダー
モルダーFXで利益が出たならば基本的に確定申告で申告をしなければいけません。
ただし、FXで利益が出たら無条件に申告するわけではなく、利用者によっては一定の利益を上げなければ申告が不要な場合もあります。
一方、たとえ損失が出たときも確定申告を行えば、節税に役立つ場合があります。
この記事では、FX取引でどのような条件に該当すれば申告が必要なのか、確定申告の手順や必要書類について解説します。
最新のおすすめ海外FX業者ベスト3!




FXで利益を得たとき課される税金について


確定申告の準備を進める前に、どんな税金がかかるのか、税率がどのくらいになるのか、納税者はとても気になるはずです。
こちらでは1年間にわたり取引を継続した場合
- FXで得た利益に課される税金とは
- 課税対象となるFXの利益とは
について解説していきます。
FXで得た利益に課される税金とは
「先物取引に係る雑所得等」に該当します。FXの場合は大きな利益が出れば、それだけ重い税率がかかるわけではありません。利益がどれくらい出たかにかかわらず、一律20.315%の税率が課せられます。
この税率の内訳は下表の通りです。
| 税 | 税率 |
| 所得税 | 15% |
| 住民税 | 5% |
| 復興特別所得税(2037年まで適用) | 0.315%(所得税15%×2.1%) |
| 合計 | 20.315% |
FXで得た利益への課税方式は「申告分離課税」を採ります。こちらは他の所得と分離して税額を計算、確定申告で納税する方法です。
課税対象となるFXの利益とは
FXは「為替差益」「スワップポイント」と呼ばれる利益が課税対象となります。この2つの利益の特徴をみてみましょう。
為替差益
為替差益は為替レートの変動で生じた利益を指します。逆に為替レートの変動で生じた損失は為替差損と呼びます。
為替差益となるのは、例えば1米ドル=100円で購入後、為替レートが円安となり1米ドル=130円となり、購入していた米ドルを円へ交換すれば1米ドルにつき30円の利益を得た、というケースがあげられます。
スワップポイント
スワップポイントは「金利差調整分」とも呼ばれ、2カ国間の金利差で発生する利益を指します。
日本のような超低金利の国の通貨を売り、経済発展が目覚ましい新興国のような金利水準の高い国の通貨を買えば、スワップポイントという収益を得ることが可能です。
FXで課される納税額の計算方法と必要経費について


為替差益やスワップポイントを得られても、その合計額すべてが課税対象となるわけではなく、必要経費があればそれを差し引いて税額を算定できます。
どのくらい納税する必要があるか
- 納税額の計算方法
- 利益から差し引ける経費
以上の2つについて解説していきます。
納税額の計算方法
課税対象を算定する場合は、まず「為替差益+スワップポイント-必要経費」の式にあてはめ計算します。
例をあげ、課税所得を算定後に納税額がどれくらいとなるのかみてみましょう。
- 為替利益:100万円
- スワップポイント:4万円
- 必要経費:12万円
為替差益100万円+スワップポイント4万円-必要経費12万円=課税所得92万円
課税所得92万円×税率20.315%=18万6,898円
こちのケースでの納税額は18万6,898円です。
利益から差し引ける経費
FXを運用するにあたり、必要経費として差し引ける支出はいろいろあります。経費として計上できるならば税負担の軽減が可能です。
FX運用に関する必要経費一覧
確定申告の際に経費として計上できるものは、主に次のような費用があげられます。
| 諸費用 | 内容 |
| 手数料 | FXの取引時に発生する手数料、銀行振込時の手数料 |
| 通信費 | FX取引で利用したインターネットの料金、電話料金等 |
| 家賃 | 賃貸住宅でFX取引専用の一室がある場合 |
| 光熱費 | FX取引で利用したパソコンやスマートフォンの電気代 |
| 受講費 | FX専門家のアドバイス料、セミナー・講座の費用等 |
| 交通費 | FXのセミナー等が開催される場所へ向かった際の交通費等 |
| パソコン・スマートフォン購入費 | FXのために購入したパソコン・スマートフォン代 |
| 書籍費用 | FX取引のために購入した書籍の費用等 |
| 消耗品費 | FX取引で使用する筆記用具、プリンターで印刷する際のインク費用 |
税務署から必要経費の税務調査をされても良いように、領収等・レシートは大切に保管しておきましょう。保管期間は白色申告が5年、青色申告が7年です。
家事按分を行う方法
光熱費をはじめパソコン購入費用や家賃等はFX取引専用に利用している場合、全額経費として計上できます。
しかし、FX取引・私用の両方で使っているなら「家事按分」をしなければいけません。更に家事按分は業務の使用を合理的に説明できるケースでのみ認められます。
例えば光熱費(電気代)を家事案分する場合、1日6時間・1週間で5日間をFXの取引に利用したとき、1日24時間・1週間を100%とすれば按分率はおよそ30%です。1ヶ月分(31日間)の電気代の総額が6万円とすると、6万円×30%=1万8,000円なので、FXの取引で使用した1ヶ月分の電気代は1万8,000円となります。
一方、家賃の場合は居住面積が50㎡で、そのうちFXの取引のスペースが20㎡であった場合、20㎡÷50㎡=0.4なので40%です。1ヶ月分の家賃が10万円の場合は10万円×40%=4万円なので、FXの取引で利用した際にかかった家賃は4万円です。



実際に使った分しか経費計上できないのね
家事按分をする際の注意点
FX取引の経費として申告できる費用は、基本的にこの取引で必要だった費用全部です。
しかし、経費として計上が認めるかは最終的に税務署の判断に従います。経費の計上が認められない支出を申告した場合、税務署から指摘されるおそれもあります。
そのため、申告前にどのような支出が必要経費として認められるか、税務署側に質問してみた方が良いでしょう。ただし、確定申告期限が迫り、必要経費と認められるか確認する余裕がないならば、無理に経費として計上する必要はありません。
FXで確定申告が必要な5つのケース


FXで得た利益が必要経費を差し引いて課税所得として残っても、直ちに納税が必要というわけではありません。FX利用者の職業によっては、一定の所得の条件を超えない限り、申告をしなくても良い場合があります。
こちらでは確定申告が必要な5つのケースについてみていきましょう。
FX利用者が個人事業主
自営業者・自由業者は毎年確定申告を行う必要があります。この方々は本業の他にFXや副業を行っている場合、どのくらい収入をあげたかに関係なく申告しなければいけません。
FXで得た利益は個人事業主も雑所得になります。なお、FX取引で事業所得に該当するのはFX取引を専門に扱い、仕事をしている方々が対象です。
年間収入金額が2,000万円を超える
給与所得者の場合は年収2,000万円を超えてしまうと確定申告が必要です。これはFX取引をしていても、していなくても確定申告の対象です。



このケースに当てはまる人は、FXで得た利益がたとえ1円でも雑所得として申告しなければいけません。
FXで年間20万円を超える利益だった
給与所得者が年末調整を既に済ました場合でも、FXで得た利益が1年間で20万円を超えるならば、更に確定申告を行わなければいけません。
年末調整には慣れていても、確定申告は初めてという人もいるはずです。20万円を超えた場合、なるべく早い段階から申告の準備をした方が良いでしょう。
こちらの場合も必要経費を差し引き、申告が必要か否かを判断します。もしもFXで得た利益が30万円でも、必要経費が20万円かかっているなら、課税所得が10万円となるため確定申告は不要です。
本業以外・FX合計で年間20万円を超える利益だった
給与所得者でたとえFXで得た利益が20万円を下回っていても、その他の副業の利益と合わせ20万円を超えた場合、やはり確定申告を行う必要があります。
FXの他にいろいろと副業をしている給与所得者は、事前にFX・副業でどれくらいの収益をあげたかよくチェックし、申告の有無を判断しましょう。
扶養へ入りFXで利益が年間38万円を超えた



専業主婦でも確定申告って必要なのかしら?
扶養家族に入っている専業主婦や学生等がFXで利益をあげ、年間所得38万円を超えた場合は確定申告が必要です。
なぜなら扶養されている配偶者・親族は、収入から必要経費を差し引き、年間合計所得が38万円を超えると扶養から外れてしまうからです。
FXで確定申告が不要なケース


給与所得者や扶養されている配偶者・親族が、一定の所得の条件を超えなければFXで利益をあげても確定申告は不要です。
その他、公的年金等の収入が年間合計額400万円以下の年金生活者の場合、公的年金以外のFX等の所得の年間合計額が20万円以下ならば申告の必要はありません。
そのため、年金生活者であってもFX等の年間所得が20万円を超えていないか、よく確認しておきましょう。
FXで損失が出ても確定申告は行うべき?


FXを運用し残念ながら損失が出てしまった場合でも、確定申告をした方がよいケースはあります。損失をうまく活用すれば、税負担の軽減が期待できます。
FXで損失を出た場合の対策として
- 繰越控除で納税額を軽減できる
- 複数のFX会社の取引を合算可能
以上の2つを解説しましょう。



むしろ確定申告をしない方が損になるケースもあります
繰越控除で納税額を軽減できる
たとえFXの運用で損失が出てしまい、まったく利益の無い状態であっても、確定申告をすれば損失の出た翌年から3年間にわたり、損失を繰り越せる仕組みがあります。それが「繰越控除」です。
つまり1年目や2年目で利益が出た場合、損失と相殺(そうさい)できるので納税額を軽減させられます。
例を挙げ、繰越控除を行ってみましょう。
(例)FXの運用で80万円の損失が出てしまった
| FXの運用年 | 内容 | 納税額 |
| 損失が出た年 | 80万円の損失を申告 | 納税不要:80万円赤字 |
| 1年目:利益10万円 | 利益10万円から損失10万円を相殺 | 納税不要:赤字繰越分70万円 |
| 2年目:利益40万円 | 利益40万円から損失40万円を相殺 | 納税不要:赤字繰越分30万円 |
| 3年目:利益60万円 | 利益60万円から損失30万円を相殺 | 納税必要:30万円が課税対象 |
この繰越控除を継続するには、1年目・2年目・3年目も確定申告を行う必要があります。
損益通算で複数のFX会社の取引を合算可能
複数の会社を利用し、FXや先物取引を運用している場合、複数社の損益を合算して納税額の軽減に役立てる方法もあります。それが「損益通算」です。損益通算を行う場合も確定申告が必要です。
例を挙げ、損益通算を行ってみましょう。
(例)A社とB社でFX運用を行いA社では50万円の利益が、B社では40万円の損失が出た
- A社:利益50万円
- B社:損失40万円
- 必要経費:10万円
利益50万円-損失40万円-必要経費10万円=0円
利益は0円なので納税不要となります。
なお、「先物取引に係る雑所得など」へ分類される取引でないと損益通算はできません。
損益通算の対象となる取引・ならない取引をみてみましょう。
| 取引 | 内容 |
| 損益通算の対象 | ・現物先物取引 ・現金決済型先物取引 ・商品指数先物取引 ・商品オプション取引 ・商品の実物取引のオプション取引 等 |
| 損益通算の対象外 | ・仮想通貨 ・海外FX会社による損益 |
確定申告書類の記入について


申告する場合は、確定申告期間(2023年提出分)である2月16日~3月15日までに行います。
申告の際は確定申告書B(所得の種類を問わず、誰でも利用可能な申告書)へ記入します。
確定申告書に記入が必要な
- 確定申告書第一表、第二表
- 申告書第三表(分離課税用)
- 計算明細書
- 所得税の確定申告書付表(先物取引に係る繰越損失用)
以上の4つについて説明しましょう。
確定申告書第一表、第二表に記載する
第一表には自分の収入・所得や社会保険料控除等の金額を記入します。第一表の記入欄は次の通りです。
| 第一表記入欄 | 記入内容 |
| 収入金額等 | 1年間の収入金額を記入、例えば給与所得ならば源泉徴収票「支払金額」から転記。 |
| 所得金額等 | 1年間の所得金額を記入、例えば給与所得ならば源泉徴収票「給与所得控除後の金額」から転記。 |
| 所得から差し引かれる金額 | 該当する控除の金額を記入、社会保険料控除の他、基礎控除、生命保険料控除等を転記。 |
第二表には自分の所得や社会保険料控除等の内容を記入します。第二表の記入欄は次の通りです。
| 第二表記入欄 | 記入内容 |
| 所得の内訳 | 所得の種類や給与等支払者の名称・所在地、収入金額、源泉徴収税額を記入。 |
| 保険料控除に関する事項 | 1年間の社会保険料控除、生命保険料控除等を記入。 |
申告書第三表(分離課税用)
第三表は、FX等の税金を確定させるため記入する書類です。第三表の記入欄は次の通りです。
| 第三表記入欄 | 記入内容 |
| 収入金額 | 先物取引の欄に収入金額を記入。 |
| 所得金額 | 先物取引の欄に所得金額を記入。 |
| 税金の計算 | 給与やFX取引、それぞれ課税対象となる所得金額を計算し記入。 |
計算明細書に記載する
FX取引の所得額を確定させる書類で、FX会社から送付される「年間損益報告書」を参考に記入していきます。
計算明細書の記入欄は次の通りです。
| 計算明細書記入欄 | 記入内容 |
| 取引の内容 | 種類や決済の方法等を記入。 |
| 総収入金額 | 差金等決済に係る利益又は損失の額の欄へ為替損益を、その他の収入欄にスワップポイントの損益を記入。 |
| 必要経費等 | FX取引でかかった手数料の他、光熱費、備品の購入費、賃料等を記入。 |
| 所得金額 | 総収入金額の総額から必要経費等の総額を差し引いた金額を記入。 |
所得税の確定申告書付表(先物取引に係る繰越損失用)
損失の繰越を行う際に必要な書類です。記入する項目は、大きく次の3種類に分かれます。
- 先物取引に係る雑所得等の金額
- 翌年以後に繰り越される先物取引に係る損失の計算
- 翌年以後に繰り越される雑損失の計算
損失の出た翌年から3年間にわたり損失と利益を相殺し、算定した金額を記入していきます。
確定申告方法と必要書類について


確定申告の際は確定申告書だけでなく、様々な書類を添付し税務署へ提出する必要があります。また、提出方法も多彩で自分にとって都合の良い方法を選べます。
こちらでは
- 申告書と共に提出する書類
- 提出方法は3種類
以上の2つを説明しましょう。
申告書と共に提示する書類
主にFXに関する書類と本人確認書類を提示する必要があります。
FXに関する書類
確定申告の際には損益報告書、それに加えて給与所得者ならば源泉徴収票が必要です。
損益報告書は、FX会社から取得するFXで得た年間損益が明記された書類です。書類には売買の損益やスワップポイント、キャッシュバックの金額、実現損益額・評価損益額の合計が記載されています。
FX会社の中には、損益報告書をダウンロードして取得できるサービスも行っているところがあります。損益報告書をどのように取得できるのか、FX会社に電話で問い合わせたり、ホームページ等をチェックしたりして、事前に確認しておきましょう。
一方、源泉徴収票とは1年間の収入や控除額、納付した所得税額が明記された書類で、お勤め先から取得します。
本人確認書類
本人を証明する書類です。マイナンバーカード(個人番号カード)を既に作成しているならば、この1点だけで十分です。ただし、カード裏表の両面コピーが必要となります。
なお、マイナンバーカードを作成していない場合、次の書類を添付する必要があります。
番号確認書類・身元確認書類の各1点を準備し提示します。
| マイナンバーカードがない場合 | A+Bの2点が必要 |
| 番号確認書類(A) | いずれか1点 ・通知カード ・住民票または住民票記載事項証明書(マイナンバーの記載あり) |
| 身元確認書類(B) | いずれか1点 ・運転免許証 ・健康保険証 ・パスポート ・身体障害者手帳 ・在留カード 等 |
提出方法は3種類
確定申告等を提出する方法は窓口・郵送・電子申告(e-Tax)の3種類です。
窓口申請
納税地を管轄する税務署へ書類を持参し、確定申告の手続きを行う方法です。確定申告期間(2023年は2月16日~3月15日)は、税務署内に特設ブースが用意され、窓口の職員に書類を提出します。
職員が書類の不備を見つけたらその場で指示してくれます。確定申告期間内に修正して提出すれば、問題なく受付してくれるので安心してください。
ただし、いつでも受付をしてくれるわけではなく月曜日~金曜日(祝日等を除く)に限定されます。また、受付時間はどの税務署も8時30分〜17時00分までです。
持参する場合は仕事の合間に時間をつくり提出する必要があるでしょう。ただし、受付時間外でも税務署に設置された「時間外収受箱」があので、収受箱へ確定申告書等を提出しても構いません。
郵送申請
確定申告書等は納税地を管轄する税務署へ郵送する方法でも可能です。税務署から自宅がかなり遠い距離にあったり、窓口で長時間待機したりするのが嫌な場合、郵送した方が便利です。
ただし、申告書の記載や提出書類の収集に手間取る等して、確定申告期間の終了日直前で提出するような場合、期間内に税務署へ届かないおそれもあります。
郵便や信書便で提出するならば、通信日付印(消印)が提出日とみなされます。余裕を持って税務署へ郵送できるよう、事前の準備をしっかりと行いましょう。
電子申告(e-Tax)
事務所または自宅にあるパソコンやスマートフォンから、24時間いつでも申告が可能な方法です。青色申告の場合は65万円控除が受けられ、本人確認書類をはじめとした添付書類の一部の提出も省略できます。
e-Taxは次の2種類の方法で利用できます。
- マイナンバーカード方式:マイナンバーカードを取得し、特設サイトから手続きを行う。
- ID・パスワード方式:税務署に赴き対面で本人確認、ID・パスワード方式の届出を行い手続きする。
いずれの場合も電子申告が利用可能となるには、行政機関での手続き等が必要です。なお、マイナンバーカード方式を希望する場合、新たにマイナンバーカードを取得するには1ヶ月程度かかるので、確定申告期限まで間に合わないおそれもあります。
忘れずに確定申告を行おう
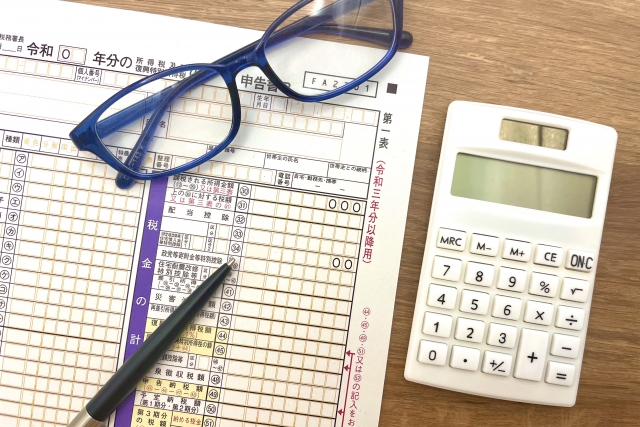
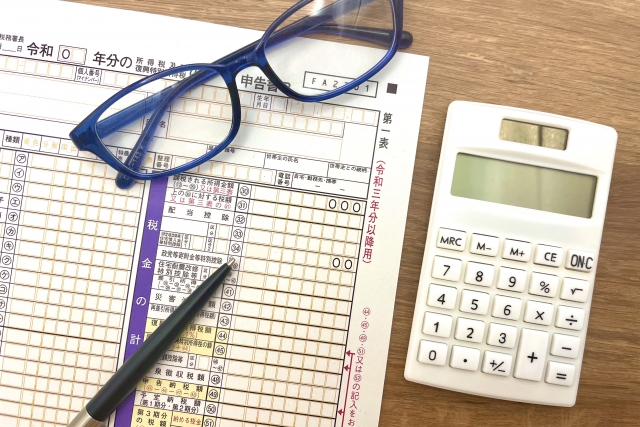
確定申告は毎年1カ月程度の申告期間が設けられ、基本的にその期間内で提出しなければいけません。FX会社から提供された損益報告書を参考に申告書へ正確な記入も求められます。
特に給与所得者は年末調整で申告する方法に慣れていても、毎年自営業者・自由業者が行う確定申告に慣れていない人も多いはずです。
確定申告に関して不明点や疑問点があれば、確定申告期間前にFX取引の申告を税務職員へ相談しておいた方が良いでしょう。事前に確認しておけば、確定申告の手続きがスムーズに進められるはずです。